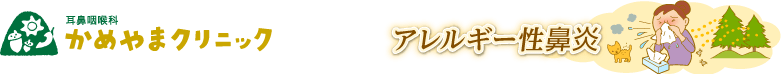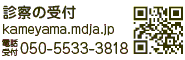山口県山口市の耳鼻咽喉科かめやまクリニック アレルギー性鼻炎解説サイト
対策について
減感作療法
減感作療法とは?
鼻アレルギー診療ガイドラインでは
アレルギー性鼻炎の治療として、3つの柱が挙げられています。
- 薬物療法
- 特異的免疫療法
- 手術
の3つです。
この2番目の特異的免疫療法は、一般には減感作療法と呼ばれています。
減感作療法そのものの歴史は古く、約100年の歴史があります。
減感作療法と薬物療法との違いを簡単に言うと、
減感作療法は、即効性は無く、年単位の治療の継続が必要となります。
しかし、薬物療法が対症療法であるのに対して、減感作療法は根治療法に位置づけられています。
WHOでは減感作療法について、以下のような見解を出しています。
- ①アレルギー性鼻炎の治療法であるが、アレルギー性の結膜炎・喘息にも効果がある。
- ②治療には専門的なトレーニングが必要である。
- ③治療期間は3年から5年がよいとされている。
- ④アナフィラキシーなど副作用の可能性がある。
減感作療法では、その方にアレルギーをおこす抗原のエキスを注射します。最初は、微量から始め、徐々に、濃度を上げていき繰り返し注射を続けます。
通常は「皮下注射」で行われますが、最近では注射ではなく、口の中に液を含む舌下免疫療法という方法が注目されています。舌下免疫療法は、現在は、まだ保険適応がありませんが、近いうちに保険適応になるといわれています。
減感作療法の手順
減感作療法を行う場合、まず本当にアレルギーかどうかを調べる血液検査を行います。
そしてそのアレルギーの原因となっている抗原液を皮下に注射します。
注射の間隔は週に1回程度で毎回少しずつ注射量を増やしてゆきます。
ある程度の量に達したら注射の間隔を少しずつ空けてゆきます。
(最終的に注射の間隔は1ヶ月または数カ月ごとになります)
以上を1年以上(理想的には3年~5年)継続します。
数年治療した後は、中止しても効果が持続すると言われています。
しかし、効果の出方には個人差があり、可能であれば間隔が長く空いても注射を継続するほうが良いと言われています。
現在、減感作療法の治療薬としては、ハウスダストと、スギの二つがあります。